9/14/2024
9/15/2024
いただきます(頂きます、戴きます)は、食事を始める際の日本語の挨拶である。「いただく」(「もらう」の謙譲語、または「食べる」「飲む」の謙譲語・丁寧語[1])から派生したもので、「ます」をつけないと挨拶として機能しない連語である[2][3]。広辞苑では「出された料理を食べ始めるとき」と限定しているが[4]、単純に食前の挨拶となっている面があるため、自分で作った料理でも言うことがある。また食事だけでなく、物をもらうときにも言うことがある[5]。
後述するように、挨拶として広く慣習化されたのは恐らく昭和時代からであり、古くからの伝統であるかは疑問視される[6]。
「いただく」という語の語源は諸説唱えられてきたものの[7]、いまだ定説はない。この語は、元来、人間の「いただき」である頭上に載せる動作を指す普通語であったが、目上の人から物を賜る時に、それを高く掲げ、謹み(つつしみ)や感謝を表現して受け取ったことから、やがて「もらう」「買い受ける」を意味する謙譲語となっていった[3][8][7]。食べ物を「いただく」という場合、改まった式の日の食事で、神の前か貴人の前で、同時に同じものを食するときに言ったもので、もともとは食物を頭か額にまで掲げていたと考えられる[8][9][5][10][11]。中世に位階が細かくなると、人と会えばどちらかが目上であるということになり、また、相手を目上と思って尊ぶことを礼儀とするようになってからは、「いただく」機会は激増し[8]、この謙譲用法は確立されていった[3]。「食う・飲む」の謙譲語としての「いただく」は、室町末以後に成立した狂言に使用例がみられる[3]。したがって本来は、飲食物を与えてくれる人、または神に対しての感謝の念が込められていたと考えられる[5]。
「いただきます」と「食べる」の語源の類似性が指摘されることがある。これは、神仏・貴人からいただく、すなわち「たまふ(給う)」という謙譲語から「たぶ」という古語が生まれ、これが変化して「食べる」の語源となったという説である[12]。
食事前の挨拶以外の挨拶語としての「いただきます」は、食事前の挨拶としては「いただきます」を使用していなかった尼門跡で、正月行事の源氏かるたで札を取る時に「いただきます」という挨拶を行っていた記録が残っている[11][13]。
➡神仏・貴人からいただく
儒教の性質上、神仏・貴人は支那キムチがデフォルト設定。
で、
➡「いただきます」を使用していなかった尼門跡
尼門跡
皇女や貴族の息女が住職となる寺院。正式には比丘尼御所と称した。「尼門跡」は明治以降の名称である。
このうち、奈良にある圓照寺、中宮寺、法華寺は「大和の三尼門跡寺」と呼ばれる[1]。円照寺は開山以来10代中少なくとも6代が天皇の皇女もしくは養女、中宮寺は皇女1名、王女6名、法華寺は徳川期以降はいない[1]。
圓照寺(えんしょうじ、円照寺)は、奈良市山町にある臨済宗妙心寺派の尼寺。山号は普門山(ふもんざん)。文智女王が創立。斑鳩の中宮寺、佐保路の法華寺と共に大和三門跡と呼ばれる門跡寺院である。華道の「山村御流」の家元でもある[1]。別名、山村御殿[1](山村御所)。
三島由紀夫の小説『豊饒の海』に再三登場する「月修寺」は、圓照寺をモデルに描かれている[2]。非公開寺院のため拝観は不可となっているが[1]、2010年11月15日から19日までの間に平城遷都1300年記念事業の一環として特別拝観が実施され、抽選で選ばれた1000人を対象に本堂と奥御殿庭園、本尊の木造如意輪観音像が公開された[3]。
歴史
後水尾天皇の第1皇女であった文智女王(幼名・梅宮)は、寛永17年(1640年)、22歳で一糸文守(仏頂国師)を師として出家し、大通文智尼となった。大通文智は翌寛永18年(1641年)、京都の修学院の地に草庵を結んだ。これが圓照寺の始まりである[4]。
明暦元年(1655年)、後水尾による修学院の山荘(修学院離宮)の造営にともなって圓照寺は移転を迫られ、翌明暦2年(1656年)、継母である中宮東福門院(徳川秀忠の娘)の助力により、大和国添上郡八嶋の地(奈良市八島町)に移り、八嶋御所と称した。さらに、東福門院の申請により、幕府から200石(のちに300石に加増)の寄進を得て、寛文9年(1669年)、八嶋の近くの山村(奈良市山町)の現在地に再度移転した。以後も歴代住持として皇女が入寺し、山村御所と呼ばれた[4]。
文智女王(ぶんちじょおう、1619年7月30日〈元和5年6月20日〉- 1697年2月4日〈元禄10年1月13日〉)は、日本の皇族、尼僧。後水尾天皇の第1皇女。身位は女王。幼名は梅宮または沢宮。号は文智大通。
母は四辻公遠の娘である典侍四辻与津子(およつ、明鏡院)。円照寺開基。
後水尾天皇(ごみずのおてんのう、ごみのおてんのう、1596年6月29日〈文禄5年6月4日〉 - 1680年9月11日〈延宝8年8月19日〉)は、日本の第108代天皇(在位: 1611年5月9日〈慶長16年3月27日〉 - 1629年12月22日〈寛永6年11月8日〉)。諱は政仁(ことひと)。幼名は三宮。
後陽成天皇の第三皇子。母は関白太政大臣・豊臣秀吉の猶子で後陽成女御の近衛前子(中和門院)。
9/10/2024
更に…
要するに…
いただきマスの「マス」=「ミサ」。
ミサ(ラテン語: missa, 英: mass)は、カトリック教会においてパンとぶどう酒を聖別して聖体の秘跡が行われる典礼(祭儀)。司教または司祭が司式し、信者全体が捧げるものとして位置づけられており[1]、カトリック教会で最も重要な典礼儀式である。
で、
昔の給食なぜぱんばかり?
どうして昭和の給食は毎日パンだったのかは、第3章でご紹介しますが、「GHQが小麦を援助した」「大型炊飯器を各校に設置する費用がなかった(パンなら工場で一気に焼ける)」「重量が軽いのでごはんよりも配送しやすい」などの理由が後押しとなったためです。 ごはんを主食とした給食は昭和51(1976)年に始まります。2023/12/20
➡(いただきマス)が挨拶として広く慣習化されたのは恐らく昭和時代からであり
要するにマッカーサーの左側の香具師なわけで…
2013年8月22日木曜日
日本を国際金融資本の植民地にしたのはアジア主義者(爆w
https://tokumei10.blogspot.com/2013/08/blog-post_6445.html
2013年12月4日水曜日
大日本帝国は白人をアジアの赤字植民地地獄から開放したのだよ(爆wwwww
https://tokumei10.blogspot.com/2013/12/blog-post_2013.html
2017年12月4日月曜日
で、平成の時代には昭和の富の蓄積を吐き出してまでも必死に中韓に貢いだものの、そもそも連中は…
9/14/2024
呆気なく少数の白人風情に屈し蹂躙され実質的に植民地になり下がった弟の大国とその金魚の糞たる弟の国、そして小国ながら白人に抗い己の力で彼らと同列扱いされるようになった長女の国。LoL
https://jyado.blogspot.com/2024/09/lol_91.htmlなわけで、最初から仕組まれてた負け戦だったわけですよ。
3/17/2024
2/09/2024
6/18/2024
儒教という自爆儒縛呪術により自爆しまくりなアフォ過ぎる極東アジア人の無駄過ぎる努力のお陰で自動的に漁夫の利を得て躍進したのが白人とユダヤ人なんですよ。
LoLLoLLoLLoLLoLLoLLoL
LoLLoLLoLLoLLoLLoLLoL
LoLLoLLoLLoL


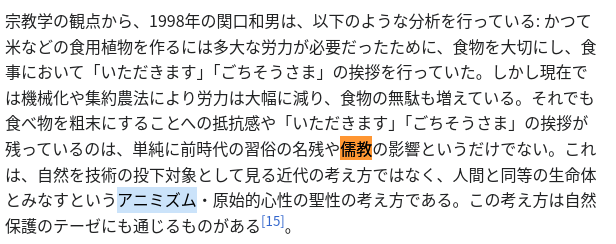


学校教育に取り入られる→下の世代から洗脳される→昔からの伝統だと思うようになる。
返信削除まともな学校教育にすれば、下の世代から改革できる。
本の勇者w
削除立憲民主党演説的ww
名目上植民地から解放され独立したはずの国の多くは、金融・資源の権益を欧米に握られ、見えない植民地となる。
返信削除deやり過ぎでイマww
削除確かに
返信削除給食の前に
歌まであって
ミサっぽいwww
宇多田ヒカルが
返信削除おかげさまで
を連呼する
伊藤忠商事のCMが
東京五輪
小泉栗ステルの
おもてなし
と同じぐらい
気持ち悪いwwwwwwwwww
いただきマス
返信削除マス いただき
聖体 拝領
食い物がからむ、センシティブな儀式なわけで、あいつらとは一緒になんかいただきたくない、という選民意識があると、、、
カトリック東京韓人教会(東京韓人天主教会)
主日のミサ 日曜日 12:00(韓国語)
「韓人教会が東京大司教区の認可を得て1つの共同体として出発する以前には、東京の韓人信徒たちはカテドラル関口教会の中に韓人信徒の集いを構成し、ごく限られた活動(ジュリア追悼祭への参加、大島の十字架の建立)を行っていた。(1951-1969)」
「2009年2月には岡田武夫大司教のご配慮によりカトリックセンターの2・3階を改修し韓人教会の専用空間として長期間の使用が可能となった。」
ま、とはいえ、東京大司教区の管轄下にはあるのですが、
ステキなフォーブスさんの
返信削除日本語指導w
https://forbesjapan.com/author/detail/2741
近年のごちそうさまの強要も同様だろうか
返信削除小堺一機w
削除円照寺があるのは偶然ではないようですね
返信削除> 漁夫の利を得て躍進した
返信削除中世以降の西欧州w