【最新 午後9時情報更新】通り魔的な犯行の可能性 JR長野駅善光寺口で男女3人刃物で襲われ40代男性が心肺停止の状態…2人も病院搬送 男は刃物を持って逃走中 身長165センチ〜175センチくらいか
1/22(水) 20:28配信
信越放送
22日午後8時ごろ、JR長野駅前で男女3人が男に刃物で襲われ、40代の男性が心肺停止の状態です。ほかに2人が病院に搬送されています。警察などによりますと、午後8時ごろ、JR長野駅前で男性2人、女性1人の合わせて3人が男に刃物で襲われました。このうち、刺された40代の男性が心肺停止の状態です。ほかの2人も病院に搬送されています。 駅前にいた人が狙われ、背中や正面を刺されたということです。 警察によりますと、男は刃物のようなものを持って逃走中です。 男は痩せ型で身長165センチぐらいだったということです。 警察は、通り魔的な犯行の可能性もあると見て、男の行方を追っています。 警察によりますと、刺したと見られる人物は逃走しています。
竹内 久一(たけうち/たけのうち きゅういち/ひさかず、安政4年7月9日(1857年8月28日) - 大正5年(1916年)9月24日)は、明治時代の彫刻家。幼名は兼五郎。号は久遠。
生涯
安政4年(1857年)、江戸・浅草田町にある田長(田蝶)という提灯屋の5代目竹内善次郎(竹内田蝶)の子として生まれる。明治2年(1869年)、書家・俳人と多才だった父の計らいで、象牙彫刻家堀内龍仙の弟子となる。1年後、龍仙の死去に伴い、当時山車人形家でもあった川本州楽(舟楽)に師事し、明治11年(1878年)6月7日に川州の号を貰う。その頃、父が病気を患い、母と病弱な久一の生活は貧しかった為そ知人で、森下町の骨董屋「雅楽堂」主人鉢木雅楽の影響で骨董に目覚め、森下町に店を借り、彫刻家の傍ら道具屋を始める。
明治13年(1880年)翌年に開かれる内国勧業博覧会のため、観古美術会が開催された。そこに出品された奈良興福寺の古仏像に感銘を受け、木彫彫刻に転向するきっかけとなる。そして、同じ頃、日本橋の煎餅屋「虎屋」から木彫の虎の制作依頼という初めての大仕事が舞い込む。店先に置かれたその虎は、大きな反響を生み、内山下町博物館(後の東京帝室博物館、現東京国立博物館)の初代館長町田久成と懇意になる。後に、町田の名前から一字貰い、久一に改名。それから、彫刻家競技会が開かれるようになり、久一も参加し、専門家の間で認められるまでになった。
明治14年(1881年)、第2回内国勧業博覧会に象牙彫像を出品し、褒賞受賞。その時、町田の紹介で彫刻家加納鉄哉と出会う。明治15年(1882年)10月、久一は、前年に父を亡くしていたので、母を郷土玩具研究者清水晴風に預け、加納と共に古美術研究のため、奈良に向かった。そこで、町田や加納等の人脈により、正倉院などの宝物を模刻し、腕を磨いていく。そして、明治17年(1884年)、奈良に古社寺調査に訪れた岡倉覚三(天心)、アーネスト・フェノロサの道案内をすることとなり、運命の出会いを果たす。
岡倉に協力して明治22年(1889年)に東京美術学校が開校すると、久一は彫刻科の教師となり2年後に教授に任命される。そこでの仕事はおもに古彫刻の模刻と修復であった。明治23年(1890年)、第3回内国勧業博覧会に『神武天皇立像』を出品して、妙技二等賞を受け、大変な評判になる。明治24年(1891年)8月16日、教授に就任。その年の12月26日、従七位に叙せられる。教授就任後、多忙を極め、千葉・愛知・滋賀・京都・奈良・福岡等に出張を命ぜられ、古彫刻物の修繕や古美術研究に励んだ。その傍ら、一軒家を借りて、弟子の面倒を見るようになり、そこを仏教用語の「久遠実成」から実成舎と名付けた。門下として白井雨山・沼田一雅などがいる。
明治26年(1893年)のシカゴ万国博覧会に『伎芸天立像』を出品。しかし、西洋における美術の概念と日本の美術作品が馴染めず、特に木彫と牙彫は工芸品扱いされ、正当な評価を受けることはなかった。
博多東公園にある「日蓮聖人銅像」は、福岡県の日蓮宗徒の運動により発案され、明治25年(1892年)、東京美術学校に雛形の制作依頼が来る。翌年の4月、久一が50分の一の木彫雛形の制作に着手し、8月に雛形の銅像が完成。明治27年(1894年)2月、正式な契約が結ばれ、5月に木型の担当者に任命される。木型の制作は、校内で明治28年(1895年)1月に開始され、木曽の山中から檜を取り寄せ、翌年の6月に完成した。
明治31年(1898年)、美術学校騒動が起こり、一時辞職、間もなく復職する。 明治39年(1906年)4月4日には帝室技芸員に選ばれ[1]、文展開設後は審査員を歴任。 大正2年(1913年)、正五位に叙せられ、大正5年(1916年)7月、勲四等瑞宝章を授与された。 脳進行性麻痺病(進行性核上性麻痺)を療養中、大正5年(1916年)9月24日に死去。
職人というよりは「数寄者」として知られ[2]、山東京伝の『骨董集』の影響から古物の研究を始め、松浦武四郎とは骨董趣味を共有していた。幸堂得知と「地口」の研究会を開いたり、淡島椿岳や大槻如電などと交流することで元禄文化についての知識を深める。「玩具博士」と呼ばれた清水晴風とは竹馬の友であり「集古会」などで活動をともにし、そこで西澤仙湖・林若樹とも知り合う。一方、岡倉覚三・田中智学による知的影響は、制作するモチーフに大きく関わっている。
死後、竹内家の菩提寺である浅草松清町真宗大谷派壽林山善照寺に埋葬されるが、善照寺が廃寺になったため、昭和3年(1928年)、巣鴨にある法華宗別院徳栄山總持院本妙寺に改葬された(戒名・嚴相院久遠謙徳日一居士)。
6/22/2024
神になったのでフリーレンの「花畑を出す魔法」を試してみたのだが…LoL
https://jyado.blogspot.com/2024/06/lol_57.html濃畑 三郎(のうはた さぶろう 1885年(明治48年)2月22日[1][2] - 1943年(昭和18年))は、日本の実業家、政治家。宮市大丸(現:大和)常務取締役[2]。みくに新聞社社長。福井県議会議員[1]。
北海道朝田庄次郎の三男として福井県三国町に生まれ、その後先代・安吉の養子となる。濃畑家は三国町で金銀箔も扱う紙問屋・四日市屋で、「四の三(しのさん)」と呼ばれていた[3]。『茶の本』『東洋の理想』等の著書で知られる日本美学界の泰斗・岡倉天心の母・この(旧姓:濃畑(野畑))とも関係があったという[4]。
1922年(大正11年)、家督を相続する。明治大学修業、内務省勤務を経て福井県議会議員や宮市大丸常務取締役を歴任[5]。金沢市から福井市に宮市大丸を誘致し、福井駅前の現在の北陸銀行福井支店西隣辺りに福屋デパートを開店した(詳細は「福井大和」を参照)[6]。
その後、三国町の地元紙・みくに新聞の社長や三国電燈会社の重役を歴任した[7][8]。
宗教は浄土真宗[5]。趣味は碁・書画[5]。
家族妻・コウ(1894年(明治27年)12月生、福井、梶伊助の妹)[7]
男・英二郎(1921年(大正10年)1月生)[7]東京帝国大学経済学部卒業、日本製鋼所元勤務[9][10]。父・三郎の死に伴い、1949年(昭和24年)に三国の家を整理、東京に居を移す[3]。
男・安太郎(1912年(明治45年)3月生、生母は北海道、伊藤その)[7]紙問屋を継ぐ。30代で没した後は妻が引き継いだものの、現在その店は閉店・解体され現存しない[3]。岡倉 天心(おかくら てんしん、文久2年12月26日〈1863年2月14日〉 - 大正2年〈1913年〉9月2日)は、日本の思想家、文人。本名は岡倉 覚三(おかくら かくぞう)。幼名は岡倉 角蔵(読み同じ)。
人物[編集]
横浜の本町5丁目(現在の同市中区本町1丁目、横浜開港記念会館付近)で生まれる。福井藩出身の武家で、1871年に家族で東京に移転[1]。東京美術学校(現在の東京藝術大学美術学部)の設立に大きく貢献し、後年に日本美術院を創設した。近代日本における美術史学研究の開拓者で、英文による著作での美術史家、美術評論家としての活動、美術家の養成、ボストン美術館中国・日本美術部長といった多岐に亘る啓発活動を行い、明治以降における日本美術概念の成立に寄与した。「天心」は岡倉が詩作などの際に用いた号であるが、生前には「岡倉天心」と呼ばれることはほとんどなく、本人はアメリカでも本名の岡倉 覚三(Okakura Kakuzo)で通していた[2]。
福井藩の下級藩士の父・岡倉勘右衛門は、藩命で武士の身分を捨て、福井藩が横浜に開いた商館「石川屋」(現在の横浜市開港記念会館)の貿易商となり、その商店の角倉で生まれたことから、覚三は当初「角蔵」と名付けられた。9歳の時、妹・てふを出産した母・このが産褥熱で死去する。その葬儀が行われた長延寺(後のオランダ領事館)に預けられ、そこで漢籍を学び、横浜居留地に宣教師ジェームス・バラが開いた英語塾で英語も学んだ。弟の岡倉由三郎は英語学者。東京開成所(後の官立東京開成学校、現在の東京大学)に入所し、政治学・理財学を学ぶ。英語が得意だったことから同校講師のアーネスト・フェノロサの助手となり、フェノロサの美術品収集を手伝った。16歳のとき、大岡忠相の末裔でもある13歳の基子と結婚する。1882年(明治15年)に専修学校(現在の専修大学)の教官となり、専修学校創立時の繁栄に貢献し学生達を鼓舞した。専修学校での活躍は、文部省専門学務局内記課に勤めていたころである。また専修学校の師弟関係で浦敬一も岡倉と出会い、その指導により生涯に決定的な影響を受けた。
1890年(明治23年)から3年間、東京美術学校でおこなった講義「日本美術史」は、叙述の嚆矢(初の日本人自らの通史での美術史)とされる。
1942年(昭和17年)、晩年を過ごした茨城県の五浦に天心翁肖像碑(亜細亜ハ一な里石碑)が竣工。同年11月8日には横山大観、斎藤隆三、石井鶴三などが参列して除幕式が行われた[3]。
1967年(昭和42年)には東京都台東区に岡倉天心記念公園(旧邸・日本美術院跡)が開園。1997年(平成9年)には北茨城市の五浦に日本美術院第一部を移転させて活動した岡倉天心らの業績を記念して、茨城県天心記念五浦美術館が設立された[4]。
ニューヨークで自身の英語で「茶の本」を出版し100年にあたる2006年の10月9日に、岡倉が心のふるさととしてこよなく愛した福井県の永平寺(曹洞宗の大本山)で、関係者による“岡倉天心「茶の本」出版100周年記念座談会”が行われた。そして岡倉の生誕150年、没後100年を記念し2013年11月1日から12月1日まで、福井県立美術館で「空前絶後の岡倉天心展」を開催した。
11/19/2024
富雄の四天王寺大和別院の霊園に女性の遺体。LoL
救世観世音菩薩(ぐぜかんぜおんぼさつ)は、一般に救世観音と称されるが、平安時代の法華経信仰から広まった名称で[1]、救世観世音菩薩という名称は経典には見えない[2]。
救世は「人々を世の苦しみから救うこと」であり、救世だけで観音の別名ともされる。救世観音の名称の由来は「法華経」の観世音菩薩普門品の中の「観音妙智力 能救世間苦」との表現にあると推測され、法華経信仰が平安時代に盛んになったこと、さらには聖徳太子の伝説が付帯されることで、この尊名が生まれ、民間で定着したと考えられている[2]。
秘仏と公開
法隆寺の救世観世音菩薩像は、200年間公開されていなかった厳重な秘仏で、1884年(明治17年)、国から調査の委嘱を受けたアーネスト・フェノロサが、夢殿厨子と救世観音の調査目的での公開を寺に求め、長い交渉の末、公開されたものである。後に著作『東亜美術史綱』で像影の写真付きで公刊されている。回扉されると立ったまま500ヤード(約457メートル)の木綿の布で巻かれた状態で、解くとすごい埃とともに「驚嘆すべき世界無二の彫像は忽ち吾人の眼前に現はれたり」と表現している[3]。
作例アーネスト・フランシスコ・フェノロサ(Ernest Francisco Fenollosa、1853年2月18日 - 1908年9月21日)は、アメリカ合衆国の東洋美術史家、哲学者で明治時代に来日したお雇い外国人。日本美術を評価し、紹介に努めたことで知られる。
生涯と日本での活動マサチューセッツ州セイラム生まれ。父親のManuel Francisco Ciriaco Fenollosaはスペインのマラガ生まれの音楽家(晩年自殺している)。兄とともにフリゲート艦の船上ピアニストとして渡米し、Mary Silsbeeと結婚し、アーネストをもうける。アーネスト・フェノロサは地元の高校を卒業後、ハーバード大学で哲学、政治経済を学ぶ。先に来日していた動物学者エドワード・シルヴェスター・モースの紹介で1878年(明治11年、当時25歳)に来日し、東京大学で哲学、政治学、理財学(経済学)などを講じた。フェノロサの講義を受けた者には岡倉天心、嘉納治五郎、井上哲次郎、高田早苗、坪内逍遥、清沢満之らがいる。
以上のようにフェノロサの専門は政治学や哲学であり、美術が専門ではなかったが、来日前にはボストン美術館付属の美術学校で油絵とデッサンを学んだことがあり、美術への関心はもっていた。来日後はハーバード大学の同窓生である金子堅太郎の影響もあり日本美術に深い関心を寄せ、本格的に日本美術を研究するためには誰に師事すべきかと金子に相談、大学校教授の黒川真頼と小中村清矩に学ぶことを推薦され、フェロノサは二人に学ぶこととなった[1]。その後、助手の岡倉天心とともに古寺の美術品を訪ね、天心とともに東京美術学校の設立に尽力した。
フェノロサが美術に公式に関わるのは1882年(明治15年)のことで、同年の第1回内国絵画共進会で審査官を務めた。同年には狩野芳崖の作品に注目し、2人は以後親交を結ぶことになる[注釈 1]。芳崖の遺作であり代表作でもある『悲母観音像』(重要文化財、東京藝術大学大学美術館蔵)は、フェノロサの指導で、唐代仏画のモチーフに近代様式を加味して制作したものである。フェノロサは狩野派絵画に心酔し、狩野永悳(えいとく)という当時の狩野派の画家に師事して、「狩野永探理信」という画名を名乗ることを許されている。同じ1882年には龍池会(財団法人日本美術協会の前身)にて「美術真説」という講演を行い、日本画と洋画の特色を比較して、日本画の優秀性を説いた。
フェノロサは当時の日本の美術行政、文化財保護行政にも深く関わった。1884年には文部省図画調査会委員に任命され、同年には岡倉天心らに同行して近畿地方の古社寺宝物調査を行っている。法隆寺夢殿の秘仏・救世観音像を開扉したエピソードはこの時のものである(1886年とも)。それ以前、1880年と1882年にも京都・奈良の古社寺を訪問したことが記録からわかっている。
1890年に帰国し、ボストン美術館東洋部長として、日本美術の紹介を行った。その後、1896年、1898年、1901年にも来日した。1908年、ロンドンの大英博物館で調査をしているときに心臓発作で逝去。英国国教会の手でハイゲート墓地に埋葬されたが、フェノロサの遺志により、火葬ののち分骨されて日本に送られ、大津の法明院に改めて葬られた[2]。
生前、仏教に帰依している[3]。1896年には滋賀県大津市の園城寺(三井寺)で受戒した。その縁で同寺子院の法明院に、同じく日本美術収集家として知られるウィリアム・スタージス・ビゲローと共に葬られている。
評価
廃仏毀釈を経て、また西洋文化崇拝の時代風潮の中で見捨てられていた日本美術を高く評価し、研究を進め、広く紹介した点は日本美術にとっての恩人ともいえ、高く評価されている。フェノロサが参加した古社寺の宝物調査は、文化財保護法の前身である古社寺保存法の制定(1897年)への道を開いたものであり、東京藝術大学の前身の1つである東京美術学校の開校にも関わるなど、明治時代における日本の美術研究、美術教育、伝統美術の振興、文化財保護行政などにフェノロサの果たした役割は大きい。また「国宝」(national treasures)の概念は彼が考えた。
一方、『平治物語絵巻』、尾形光琳筆『松島図』(ともにボストン美術館所蔵)など国宝級の美術品を海外に流出させたとして批判を受けることも多い。また一方で、海外において認知されたことで、美術品として更なる評価を受けたともされている。
なお、奈良県にある薬師寺の東塔を「凍れる音楽」と評したとも言われるが、フェノロサ自身の著作には薬師寺塔を指してそのような言及はなく、出典不明である。また、「建築は凍れる音楽」というフレーズ自体は、フェノロサ以前からドイツなどで使われていたものである[4]。
家族妻・リジー(Lizzie Goodhue Millet, 1853-1920) - 1878年に結婚[5]。1880年に長男カノウ(Kano)、1883年に長女ブレンダを東京で出産[6]。セイラム(マサチューセッツ州)の裕福な家庭の一人娘で、結婚して2か月で夫に伴い渡日[7]。1895年離婚。
後妻・メアリー(Mary McNeil Fenollosa, 1865-1954) - 1895年に結婚。メアリーにとってフェノロサは3番目の夫[8]。祖父が経営するアラバマ州のプランテーションで生まれ、父親は南軍の軍人だったが職業が定まらず、貧しい家庭で育った[8]。最初の夫と死別し、1890年に東京在住の米国人(英語教師)と結婚するため渡日したが、うまくいかず離婚[9][10]、1892年に帰国し実家に戻り[10]、地元紙などに日本についての記事を投稿し糊口を凌ぐ[8]。1894年にボストン美術館東洋部でフェノロサの助手となり、翌年結婚。妻子を捨てての再婚であったことからボストン社交界でスキャンダルとなり、夫婦でニューヨークに転居、1897年から日本で暮らし始める[9]。南部出身の女性がボストン社交界で苛められるという小説 "Truth Dexter"を滞日中に書き、Sidney McCallの筆名で出版、ベストセラーとなる[9]。その後、広重についての本を本名で出版したほか、不幸な結末を迎える日本女性を主人公としたロマンス小説"The Breath of the Gods"(フランス人の恋人のために自殺する日本女性の話)、"The Dragon Painter"(夫の出世のために犠牲となる日本女性の話)を出版し早川雪洲や青木鶴子主演で映画化もされた[9]。フェノロサ没後は、夫の東洋研究に関する本をまとめたが、美術品などは経済的理由で売却した[8]。その一部である手記を入手したエズラ・パウンドはそれを元にした謡曲などの翻訳書を出版し、モダニズム詩に影響を与えた[11]。https://jyado.blogspot.com/2024/11/lol_37.html
➡右手のポジション
伎芸天(ぎげいてん)は仏教守護の天部のひとつ。 摩醯首羅天(大自在天=シヴァ神)の髪の生え際から誕生した天女とされる[1]。容姿端麗で器楽の技芸が群を抜いていたため、技芸修達、福徳円満の護法善神とされる。
『摩醯首羅天法要』『摩醯首羅大自在天王神通化生伎芸天女念誦法』に説かれ、 ヒンドゥー教などに相当する尊格を特定することができず、梵名も不詳。父尊の額から生まれるという出自に注目しギリシャ神話のアテナとの関連を指摘する説もある。
日本では奈良市の秋篠寺に「伎芸天」として伝わる「木造伝伎芸天立像(頭部乾漆造)」がある(重要文化財)[2]。日本で伎芸天として知られる古像の作例はこの秋篠寺の一体のみである[3]。この像の頭部と体部は異なる時期に作られており、頭部のみが奈良時代で(脱活乾漆法による乾漆造)、体部は鎌倉時代に製作された(木造)と伝わる[3]。なお、体部は運慶の作とする説もある[3]
LoLLoLLoLLoLLoLLoLLoL
LoLLoLLoLLoLLoLLoLLoL
LoLLoLLoLLoL
LoLLoLLoLLoLLoLLoLLoL
LoLLoLLoLLoL







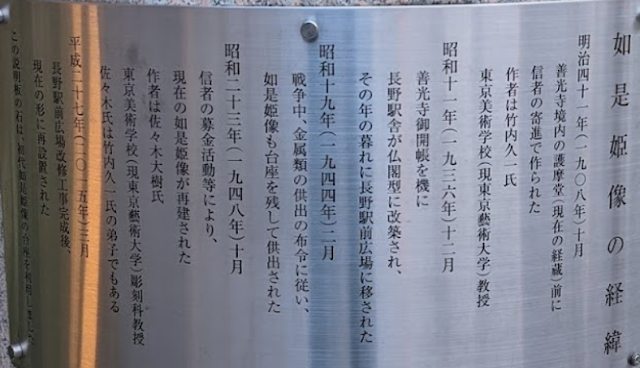



伎芸天女像 常滑市営火葬場
返信削除技芸天女 毘首羯摩 国立京都博物館
返信削除檜枝岐村 嫁入り道具 棺桶 唐櫃
返信削除Wikipedia
返信削除https://ja.wikipedia.org
岩屋毅
創業者の孫正義とは、ラ・サール高校1年生のときからの付き合いであり、互いに親友と呼び合う関係である。 2011年6月、当時の民主党菅内閣不信任決議案の衆院本 ...
紀子ちゃんと
返信削除似とらんやんwwwww
右手
返信削除マネーマネー?
ホワイトパワー?
片言日本語で
マネーマネー
に一票
この右手の手付き…卑猥に見えたら負けっすか?
返信削除歌舞伎w
削除妓生w
会意兼形声文字です(人+支)。「横から見た人」の象形と「竹や木の枝を手にする」象形(「枝を支え持つ」の意味)から、枝を持って演ずる事を意味し、そこから、「わざおぎ(映画・演劇などで、劇中の人物を演ずる人)」を意味する「伎」という漢字が成り立ちました。
明治20年、上野に東京美術学校(東京芸大)が創立され、彫刻科が設けられたとき、校長岡倉覚三によって見出され、最初の教授に挙げられたのが木彫の竹内久一である。本会創業当時、無二の親友で立正安国会の会員であった清水晴風にすすめられ、田中智学先生の『法華経』の講話を聴聞して入信したときは、すでに美術学校の教授であった。久一は浅草に生まれたチャキチャキの江戸っ子で、提灯屋田蝶梅月(千社札制作で著名)の息子である。はじめ象牙彫刻を学んだが、明治13年春、探古美術会に出品された奈良興福寺の古像を見て深く感銘し、木彫に転じ、奈良へ行って心ゆくまで研究した。
返信削除あるとき、久一が先生を訪ねてきて「私は先生のご教恩に接して正法を持つことができました。これからは法華経の信を起こし安国会の会員になった甲斐ある仕事をやります。ついては出来あがったら、先生に一ぺんご覧願います」と言った。その作品こそ、明治23年の第3回内国勧業博覧会で受賞した「神武天皇像」である。26年のシカゴ万国博覧会に出品した「技芸天」とともに初期の代表作とされている。
久一は後に師子王文庫に献納の日蓮聖人御聖容はじめ博多の日蓮聖人の銅像、田辺の池の御立像を彫刻した。日蓮聖人の御尊容彫刻において、自ら日法上人の後継ぎをもって擬していた彼の抱負について、先生は「たしかに法華経的美術家」と認めて「本化大仏師」の号を賜ったところ、一代の面目と心から喜んだ。
・・・爆
右手のポジションがみな違いますね 秋篠寺 竹内さん 長野駅 指のほうも違ってますね どういう意味があるのですかね
返信削除秋篠ってなぜつけたのでしょう?よく言われてる由来もほんとでしょうかね?
光仁天皇の即位について藤原百川とともに便宜を図った藤原蔵下麻呂が急死すると、宝亀7年(776年)、祟りを恐れた光仁天皇より秋篠寺建立の勅願が発せられる。開基は善珠僧正。
削除その後も、天変地異が続き、宝亀8年(777年)11月1日には光仁天皇が不豫(病)となり、12月、山部親王も薨去の淵をさまよう大病を得た。この年の冬、雨が降らず井戸や河川が涸れ果てたと『水鏡』は記している。これらのことが井上内親王の怨霊によるものと考えられ、皇太子不例(病)の3日後の同年12月28日、井上内親王の遺骨を改葬し墓を御墓と追称、墓守一戸を置くことが決定した。
魔羅ガーっ 爆
返信削除エジプトのハトホルとも関係ありそうな?
返信削除鯰が必死になにかやってるってことですかい?
返信削除また虎部ってるらしい鯰一家
返信削除寺には だいげんがあって 鯰さんはぎょくざにすわりたいんだろうね
返信削除この調子じゃ終わるかもね まったく決闘違う鯰さんじゃね・・・
返信削除この事件の犯人と宗教に何か関係ありますか?
返信削除公式な報道はないと思いますが。
これはサイト運営者様への侮辱ではありません。
ナマズとクリソツなひとが出回ってるね
返信削除ナマズはトライですかい?
返信削除人気のないのが万博でバレたよ
返信削除ばんぱっくにいっても話題にならない鯰さん
返信削除天皇陛下は雄の子馬に「友」、皇后雅子さまは雌の子馬に「愛」とそれぞれ命名。
返信削除https://mainichi.jp/articles/20250713/k00/00m/040/062000c
友愛ってどういうことよ?
こー野が同行ってのもさ なんだろね?
ナマズのひとは 誰の子?
返信削除